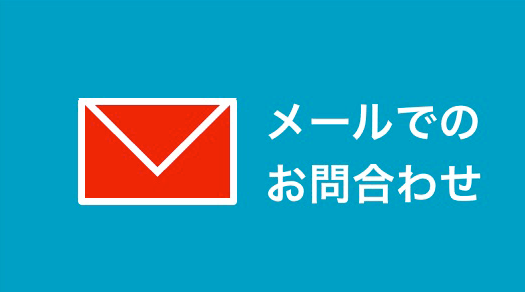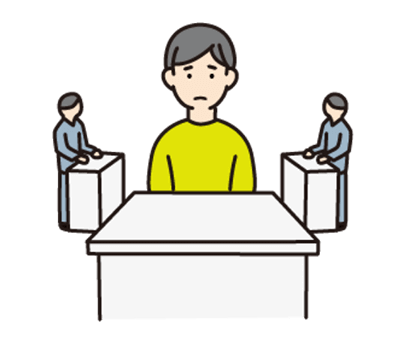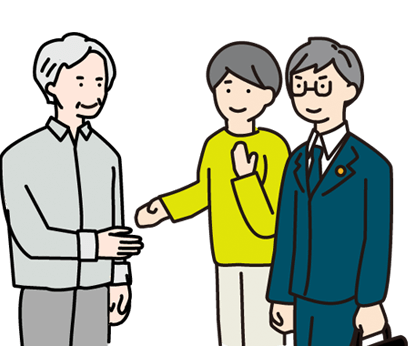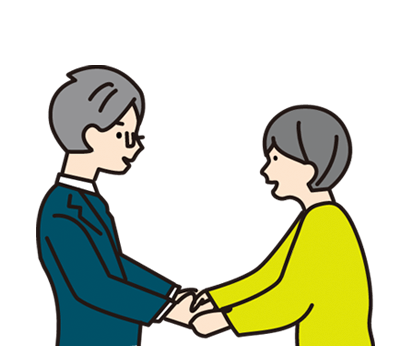釈放のための刑事弁護活動①
- 2019年11月17日
- コラム
釈放のための刑事弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。
◇事例◇
高石市に住むAさんの夫は、Aさんの出産を機に、これまで勤めていた大手保険会社を退職し、独立して保険代理店を起ち上げました。
新規の顧客を獲得するために、Aさんの夫は、独立する少し前から、以前勤務していた会社のネットワークシステムに、自宅のパソコンから不正にアクセスし、会社の顧客情報を盗み見ており、最近になって、このことが以前勤めていた会社に発覚してしまいました。
以前勤めていた会社に刑事告訴されたAさんの夫は、不正アクセス禁止法違反の容疑で、大阪府警に逮捕されてしまったのです。
逮捕の知らせを聞いたAさんは、まもなく出産を控えており、夫の一刻も早い釈放を望んでいます。
(フィクションです。)
ご家族が警察に逮捕された方のほとんどが、逮捕された方の一日でも早い釈放を望んでいます。
そこで本日は、警察に逮捕された方を早期に釈放するために、弁護士がどのような弁護活動を行うのかについて、堺市の刑事事件専門弁護士が解説します。
◇釈放◇
釈放とは、刑事施設に収容されている在監者の身柄拘束を解くことをいいます。
逮捕や勾留されてしまうと、多くの場合、警察の留置場に収容されることになり、会社や学校には行けないことはおろか、外部との連絡が途絶えてしまいます。
それ故に、身柄拘束が長期にわたると、退学や解雇されたりするおそれがあります。
釈放されると、例え捜査が継続したとしても、元の生活に戻り、学校や会社に行くことが出来ます。
また早期に釈放されれば、事件が周囲の人に知られるリスクも小さくなります。
そういった意味で、逮捕・勾留後の早期釈放に向けた弁護活動は、刑事事件専門弁護士の大きな役割といえるでしょう。
◇起訴前の釈放◇
~検察庁に送致される前~
警察官は、容疑者を逮捕した場合、留置の必要があると判断した場合には、逮捕後48時間以内に書類とともに身柄を検察官に送致しなければなりません。
逆に留置の必要がないと判断した場合には、直ちに容疑者を釈放しなければなりません。
逮捕された事件の内容によっては、逮捕から48時間以内に釈放されることもありますが、送致前に警察の判断で釈放される割合は少ないでしょう。
ただ送致までに弁護士を選任することができれば、担当の弁護士から逮捕した警察に対して、送致せずに早期に釈放するように働きかけることができます。
~検察庁に送致されてから勾留請求までの間~
事件が検察官に送致されると、検察官は、まず被疑者に対して弁解録取(被疑者の弁解を聞いて弁解録取書を作成する手続き)を行います。
そのうえで、留置の必要がないと判断したときは直ちに釈放しますが、留置の必要があると思うときは、送致を受けて24時間以内に裁判官に勾留を請求するか、公訴の提起をしなければなりません。
実務上、直ちに公訴提起を行うことは極めて珍しく、釈放して在宅による捜査を継続するか、勾留して身柄拘束を継続して捜査をするかのどちらかが、ほとんどです。
勾留が裁判官によって認められると、最大で20日間の身体拘束となりますので、当然、できる限り勾留を回避したいところです。
そのため弁護士は、検察官による勾留請求前の段階においては、検察官に対して、意見書を提出する等して、勾留請求しないよう働きかけます。
弁護士の働きかけが功を奏せば、被疑者の勾留を回避することができます。
~勾留請求から裁判官が勾留決定するまでの間~
検察官が勾留請求をした場合、勾留を決定するかどうかの判断は、裁判官が行います。
そこで、検察官が勾留請求を行う意向である場合、弁護士は、裁判官に対して勾留の決定をしないように働きかけます。
勾留は、裁判官が勾留の理由や必要性があると判断した場合に認められます。
ですから、弁護士は、裁判官に対して、被疑者や、そのご家族等から聞き取った事情や収集した証拠をもって、勾留の理由や必要性がないことを主張します。
裁判官との面会や意見書の提出を通じて、弁護士が説得することにより、裁判官が勾留を認めなければ、被疑者は釈放されることとなります。
~勾留決定後~
裁判官から勾留を決定いた後でも、この決定に対して不服を申し立てることが可能です。
裁判官が行った勾留決定が間違っていることを主張して、取消しを求める不服の申立てを準抗告といいます。
準抗告は、一度なされた裁判官の決定を覆すことを要求する手続きですから、ハードルは高く、認められる確率は低いのが実際のところです。
また、準抗告以外にも勾留決定の判断を取り消すよう、裁判官の職権発動を求めて、勾留の執行停止を求めることもできます。
勾留の執行停止は、被疑者に入院の必要性がある場合や両親・配偶者等の危篤または死亡した場合などに勾留の執行を停止する手続きであり、裁判官が職権で判断します。
このような事情がある場合、弁護士は、裁判官に面談を申し入れるなどして、勾留の執行停止を促します。
明日のコラムでは、起訴後の釈放(保釈)について解説します。